オジー・オズボーン追悼 偉大なるオジーよ…永遠なれ…

Simackyです。
2025年7月22日(火)、オジー・オズボーンが逝去しました。
享年76才。
オジーの長い長い旅が終わりました。
長かった物語もここに完結します。
1948年生まれのオジーは、5年前になくなった私の父と同い年です。
なので、私は、半分、オジーのことを自分の父親のように思っていた部分があります。
オジーとの出会い。
それは、中学生の時にプロレスをテレビで見ていた時。
友達と一緒に大好きだったヘルレイザーズというタッグチームが、入場曲で『ヘルレイザー』を流していて、それがあまりにもかっこよくて、大好きになったのがきっかけです。
それが私にとっての洋楽入門であり、ロック入門であり、ヘヴィメタルへの入門でした。
私にとって、こんな面白い、楽しい、スリリングな音楽・世界があることを教えてくれた人。
若い頃は彼のインタビュー記事を貪るように読みました。
人生の先輩としてのオジーの言葉は、私にとって、まるで父親が息子に語りかけるように、いや、それ以上に私に響いたものです。
・・・・・・
さて、お酒は手元に準備できたでしょうか?
そしてオジーの音楽を流す準備はできたでしょうか?
今宵ははオジーの弔い酒です。
存分に飲みましょうぞ!
ゆるりとお付き合いください…。
偉大なるオジー①本物にこだわった
オジーって言う人は審美眼が飛び抜けている人だったと思います。
いや、正確に言うと、自分の審美眼で『良い』と思ったものには妥協しない人。
逆に言うと、『良い』と思えないものは絶対演りたくない。
とことん芸術家肌なんです。
けどね、オジーは一流のエンターテイナーでもあります。
ファンの喜ぶ顔を想像すると、ドラッグやアルコールでフラフラになっていたって、ステージではエネルギーの最後の一滴まで絞り切るパフォーマンスを見せるんです。
皆に期待されると、本能的にそれに答えてしまうんです。
それはミュージシャンとしてプロフェッショナルだということを意味するんですよ。
オジー・オズボーンに求められるものを全て満たし、ファンを満足させる。
ファンが満足しない独りよがりの作品は作らない。
つまり、それは言い換えると、『売る』っていうことにも妥協しないっていう姿勢に繋がっていたのだな、と。
オジー・オズボーンの作品がいついかなる時も、かなり高いクオリティを維持しながら、高いセールスも維持しているのは、このオジーの2つの要素がいつだってせめぎ合っているからです。
けれども、この2つを両立するのは至難の業なんです。
いつだって両立できているわけではありませんよ。
1980年に『ブリザード・オブ・オズ』でソロデビューし、実質最後のアルバムとなった『ペイシェントNo.9』までのオリジナルアルバム数は12作品。
この中にはプロミュージシャン・オジーとしては仕事を全うした(=売れた)けれども、芸術家・オジーとしては納得していない作品もあります。
『罪と罰』『オーディナリー・マン』なんかが、彼のインタビューから、それに該当することが伺えます。

『THE ULTIMATE SIN』(罪と罰)
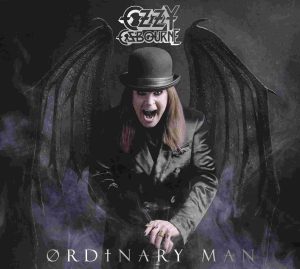
『オーディナリー・マン』
どの作品が良いのか悪いのか?という話をしているわけじゃありませんよ?
「これらの作品が一番好きだ!」
っていう人がたくさんいますしね。
彼はいつだって、自己表現の究極と、セールス的な充実、この2つを両立させようともがき続けてきた、ということを伝えたいんです。
その意味でいうと、彼にとって理想に近づけたのがデビューからの3作品や『ノー・モア・ティアーズ』あたりの作品なのだと思います。
彼の口から出てくる『満足の行く作品』の代表例ですよね。
そして彼の審美眼は、自己の作品だけではなく、一緒に演奏するメンバーにも及びます。
特にギタリスト。
単にギターが上手いというだけではない。
自分が求める究極の音楽を一緒に体現できる人間は誰なのか?
それを彼は一発で見極めます。
ランディ・ローズ、ジェイク・E・リー、ザック・ワイルド…
彼ら伝説のギタリストを発掘したオジーの才覚は評価されてますが、あまり知られていない事実があります。
実は、実際のオーディションでは
大してオーディションらしきことはしていない
という事実です。
歴代ギタリストのインタビューを読むと皆そういう感じで採用されてます。
実はそうなんですよ。
彼はちょっとアドリブで弾かせてみるだけで、そのギタリストがメロディを大切にしている人なのか?テクニックのひけらかしに走っている人か?リズム感がある人か?オリジナリティはあるのか?人まねではないか?自分のメロディが乗せやすいタイプのリフか?
そういうことを見極めることができたのだと思います。
スーパーギタリストに出会えたのは、決して運だけではありません(こんな悪運があってたまるか)。
とことん本物を求め、とことん本物にこだわったオジー・オズボーンの姿勢が、数々のスーパーギタリストを、そして 傑作を世に生み出したのだと思います。
偉大なるオジー②人生が終わる間際までロックスター
オジー・オズボーンという人は、数々の伝説(奇行)を残しています。
今更ここでそれは語りませんが、それら奇行の数々を彼は全て笑い飛ばしながら、生きていました。
一度彼の自伝である『アイ・アム・オジー』を読んでみてください。
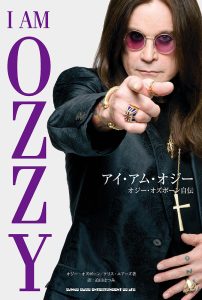
そこにはオジー独特のユーモアで笑い話に変えられた数々の奇行が綴られています。
根本的に人間が明るいんですよ。
人間が面白いんです。
そしてその根底には強さがあります。
グランジ・オルタナティブミュージシャンの歌詞のように、人や時代、運命のせいにしたり、恨んだり、といったことはほぼありません。
自分の人生に起きたことを全て受け入れて、背負っています。
それは全て自分の責任なのだ、と。
「愚痴こぼしたってどうせ誰も聞いてくれやしないだろ?運命を呪ったってそれで何か解決するわけじゃない。だったら笑い話にしてせめて笑いでも取らなきゃな」
そう、思っていたのかどうかは分かりませんが、彼の自虐ネタの、まあウィットに飛んでいること!
人としての器の大きさが違うというか、くぐり抜けてきたものが違うというか。
そしてそうしたウィットやユーモア、そして強さは、ブラック・サバスのオリジナルメンバー全員が持ち合わせているのが凄い。
オジーバンドにはたくさんの大物ミュージシャンが出たり入ったりしましたが、誰もオジーと同格の存在感を放つことはできません。
けれども、1990年代にはいって20年ぶりに再結成した時に、オリジナルメンバーでステージに立つと、まぎれもなくブラック・サバスなんですよ。
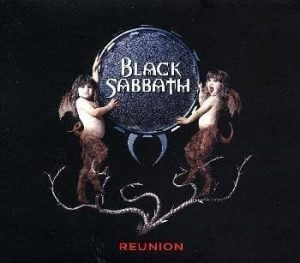
オジーが1人だけソロで大成功をしているからと言って、オジーバンドにはならない。
ブラック・サバスのいちボーカリスト・オジーになってしまうんです。
それはオジーが矮小化したということではなく、オリジナルメンバーの個性と存在感が圧倒的だからそうなってしまうんです。
それを本人も分かっていたのでしょう。
自分はどこまでいってもブラック・サバスのいちボーカリストだ、と。
彼がキャリアに終止符を打つための場として選んだ最後の舞台は、オジー・オズボーンとしてではなく、ブラック・サバスでした。
当然、アメリカではなく、彼らの地元バーミンガム(イギリス)です。
『バック・トゥ・ザ・ビギニング』
ですね。

開催は2025年7月5日。
なんと亡くなる2週間前。
ということはですよ?
パーキンソン病に蝕まれたオジーは、もしかすると、もう自分の余命が幾ばくもないことを分かっていたのかもしれません。
すでに自分の足で立って歩くことさえできなかったのですから。
もはやファンの前で公演を行う体力は残っていない。
けれども、オジーは残りの人生のためにほんのちょっぴり残されたエネルギーを、この公演に一滴残らず絞り出したのだと思います。
まるで20216年に最後のアルバムをリリースして亡くなったデビッド・ボウイじゃないですか。
癌に蝕まれてボロボロの体の全てのエネルギーを、最後の『ブラック・スター』に込めて彼は逝きました。
アーティストとして、ロックスターとして、最後まであがいて、前向きで倒れて逝ったんです。
この死に様に感銘を受けた部分があるんじゃないかな?
オジーは生前、
「ロックンローラーの象徴と言えば誰を挙げますか?」
という質問に、迷うこと無くデビッド・ボウイを挙げていたので、彼の死に様にはかなり感じ入ることがあったのかもしれませんね。
そして、オジーのそんな生き様は、『バック・トゥ・ザ・ビギニング』に参加したメタリカを始めとする後輩ミュージシャンたちの心に深く刻まれたはずです。
偉大なるオジー③愛嬌と寛容の人
オジーってクレイジーな話題には事欠かない人だったのですが、じゃあ、彼と付き合った人が、一緒に音楽を制作したメンバーなんかが
「もう、オジーのわがままに振り回されるのはまっぴらだよ。」
「彼が王様だから。彼の言うことにただ従うだけさ」
みたいなことを言っていることってまずないんですよ。
オジーはサバス時代と違い、ソロになってからはたくさんのセッションミュージシャンを起用しました。
色んなアーティストと共作しました。
けれども、私の知る限りそんなことを言っている人の記事を読んだことがありません。
世の中にはアクセル・ローズ(ガンズ)だとか、プリンスだとかロジャー・ウォーター(ピンク・フロイド)だとか、YOSHIKIだとか(笑)、独善的で完璧主義者でワンマンで全てを自分一人で決めるような人っていますよね?
オジーはそういう人たちのような制作プロセスとまったく逆なんです。
逆に
「オジーが『もっと思いっきりやれ!自分を出せ!』って言ってくれたんだ」
みたいな話ならどれだけでも出てきます。
「お前のベースの音がもっと聞きたいんだロバート(トゥルージロ)!」
みたいな。
あの愛嬌のある顔でニヤリとしながら。
あんなにクレイジーなのに良いヤツなんです(笑)。
コウモリや鳩の首は噛みちぎっても
「この下手くそが!お前は明日からスタジオに来るな!」
ってぶん殴ったり、唾を吐きかけたりなんかしないんです。
ランディ・ローズをはじめとする歴代のギターヒーローを見出すことが出来たのも、このオジーの寛容さにあるのだと思えてなりません。
“見出した“というより、“開花させた”という表現の方がぴったりなんだと思います。
どんなにキラリと光る才能を持っていたって、それに指示を出す人が個性やオリジナリティを台無しにして、自分の発想の範囲の中のことしかやらせないのであれば、それは所詮セッション・ミュージシャンの域から出ることはなかったでしょう。
オジーはきっと“化学反応“を楽しんでたんだと思います。
そのミュージシャンが見せてくれる自分とは全く違う発想に刺激を受ける。
それがオジー本人の驚きや興奮に繋がり、自分自身ももっともっと夢中になっていく。
親と子ほども歳が離れたミュージシャンたちと音楽制作をともにすることが出来る。
これってオジーの突出した才能だったのだと思います。
おわりに
あれだけ破天荒にアルコールとドラッグをやってきたオジーが、70過ぎまで長生きするなんて当時の誰が考えたでしょう?
ましてや、70歳を過ぎてもニュー・アルバムをリリースしている姿を誰が想像できたでしょう?
パーキンソン病を公表した後に2枚出したんですよ?
「やっぱりオジーは鉄人なんだ」と、「100才くらいまで生きるんだ」と思ってました。
「70代のうちにもう1枚くらいはニューアルバム出すのでは?」
そんな期待さえ抱いてしました。
けれどもそれは叶いませんでしたね。
彼の死を
「早すぎた、残念だ」
とは思いません。
オジーは自分の76歳という天命を全うし、ランディのもとに帰るんですよ、きっと。
オジーにはただただ感謝の気持しかありません。
なので最後にマサさん(伊藤政則)のこの言葉を私も送ります。
「ありがとうオジー。ありがとう、ジョン・マイケル・オズボーン」
Simackyでした。
それではまた…。
このサイトではこれまで、オジー・オズボーン、ブラック・サバス(オジー在籍時)の記事をアルバムごとに解説してきました。
それらの記事を読みながら、オジー・オズボーンという愛すべき男の人生に思いを馳せてみてください⇩
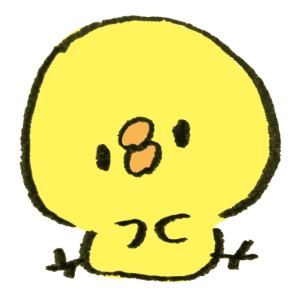

Ozzyについての考察ありがとうございました。私も全く同感です。そうだよなあと思いながら読ませて貰いました。
私は1983年の中1のときにBark At The Moonを友達の家で聞かされたのがOzzyとの最初の出会いでした。カセットテープにダビングさせて貰い毎日聴いていました。OzzyとJakeのコンビは最強でした。次のUltimate Sinも大好きでした。中3の3月でした。高校に入ってすぐ、ランディローズ時代も聴きたくなってファーストを買いました。激ハマりしました。Jakeは難し過ぎて全く弾けませんが、Randyは何とかなりました。87年にはTributeが出て泣きました。少ししてJakeが辞めたとの報をBURRN!で読みショックでした。ザックワイルドのノー・レスト・フォー・ザ・ウィキッドを聴きましたがピンと来ず、そこからOzzyから離れていきました。ノー・モア・ティアーズ、オズモシスは聞きはしましたが91年、95年その時だけでした。それ以降のOzzy新作は全く聞きもしていませんでした。が、Ozzyを忘れていたわけではなく、Brizard Of Ozz, Diary Of Madman, Bark At The Moon, The Ultimate Sin, サバスの確認アルバムはずっと聴き続けてきました。Ozzyの病があそこまで深刻とは思っていなかったので、ラストライブはいつか日本にも来るやろと簡単に考えていました。
今でもOzzyがいなくなったのが信じられず、持っていなかったノー・モア・ティアーズ以降のアルバムを一つ一つ手に入れ毎日聴いています。一昨日オズモシスを買い、30年振りに聴きました。
後年のOzzyを辿る旅を続けます。
ゴマさん、お久しぶりのコメントありがとうございます!
『バーク・アット・ザ・ムーン』がリアルタイムだったんですね。
私の場合は『ノー・モア・ティアーズ』なので、大先輩に読んでいただき光栄です。
やっぱりリアルタイムの世代の方にとってジェイクは特別な存在のようですね。
オジーに関しては全アルバム1枚1枚熱い思いを込めて解説してますので、“後年のオジーを辿る旅“のお供にしていただけたら、この上なき喜びです。