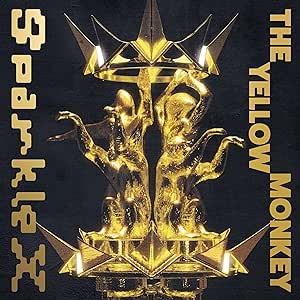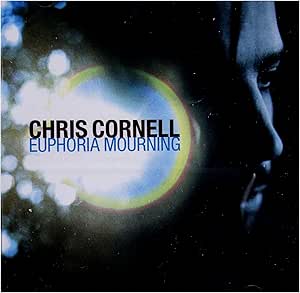『ダウン・オン・ジ・アップサイド』サウンドガーデン 全てが詰まった完成形
本記事はプロモーションを含みます。

どうもSimackyです。
今回はサウンドガーデンが1996年にリリースした5作目のオリジナルフルアルバム
DOWN ON THE UPSIDE
(ダウン・オン・ジ・アップサイド)
をたっぷり語っていきたいと思います。
大っ好きなアルバムですね。
サウンドガーデンで一番好きだった時期が長いです。
やっぱり前作『スーパーアンノウン』が大人気アルバムなので、本作は影が薄くなりがちなんですが、これ凄いアルバムなんで是非ともこの記事を機会に再評価されることを願います。
タイトルがなんかありきたりの英単語が並んでるんで、『BADMOTORFINGER』とか『SUPERUNKNOWN』みたいなインパクトがないんですよね。
グーグル和訳では
「逆境や困難を乗り越えて良い面を見いだす」
と出ました。
ええぇ?
らしくないほどポジティブですね~(笑)。
そう、本作は『らしくなさ』も重要なポイントになってきますからね。
そのあたりは後ほど解説しますよ。
それでは前作『スーパーアンノウン』から本作に至るまでの経緯から語っていきましょう。
バンド史上最大ヒットからのその後のツアー
1994年3月にリリースされた前作4作目のオリジナルフルアルバム『スーパーアンノウン』は、彼らとしては最初で最後の特大ヒットとなります。

『スーパーアンノウン』
発売初週だけで30万枚セールスを超え、世界各国でチャートのトップ10入り!
本国アメリカでも1位を獲得し、アメリカだけでも600万枚を超えるセールス!
カットした5曲のシングル曲は軒並みヒット!
そのうちの2曲『ブラックホールサン』『スプーンマン』はなんと1994年グラミー賞をダブル受賞!
最終的には全世界で1000万枚を超えるセールスのモンスターアルバムとなり、現在では1990年代のグランジ・オルタナティブロックを代表する名盤どころか、1990年代のミュージックシーンを代表する大名盤となりました。
「シアトルグランジの元祖」
「ニルヴァーナも認める音楽的実力」
などと呼ばれながらも、商業的な面では後輩たちに完全に先を越されて辛酸を舐めてきた彼らでしたが、ここにきてようやく面目躍如となったわけですね~。
まあ、辛酸なめたゆうても彼らがそれまで『売る』ことや『有名になること』に積極的でなかったことは作風からも明らかで、そりゃニルヴァーナやアリスの作品と聴き比べれば一聴瞭然。
ソニック・ユースやダイナソーJr.などの’80年代からアンダーグラウンドでやってきたバンドならともかく、あれだけシアトルシーンが注目され、その中心的バンドとしてもてはやされても、浮足立つこともなくしっかりと地に足つけて進んできたのは、グランジ四天王ではサウンドガーデンだけでは?
こういう売れ方ってレッチリに近いですよね。
レッチリも長い時間かけてじわじわ売れてきて、5作目『ブラッド・シュガー・セックス・マジック』でドカンとブレイクしましたから。
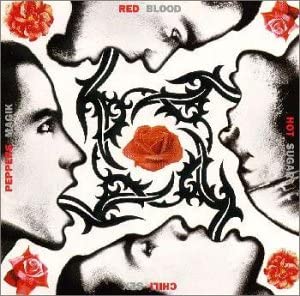
1991年『ブラッド・シュガー・セックス・マジック』
まあ、レッチリの場合は最初の2作があまりにも売れなくて、レーベルから契約を一度は切られようとしていたので、あそこまで地道な歩みではないですが(笑)。
サウンドガーデンの場合、前作の3作目『バッドモーターフィンガー』の時点で100万枚は軽く超えるセールスを記録していたんです(250万枚くらいは売れてた)。

それなのに彼らへの扱いときたら、ヘッドライナーでのツアーを組むことも出来ず、やれニール・ヤングだ、やれガンズ・アンド・ローゼズだ、やれスキッド・ロウだのオープニングアクトでしかなかったんですから!
酷くね?
スキッド・ロウなんて1989年メジャーデビューの同期ですよ?
そりゃあさ、まだこの時点でのサウンドガーデンが、アリーナやスタジアム級を単独で埋めれる人気は全然ありませんでしたよ?
けれども、オープニングアクトなんてやったって、客のお目当てはヘッドライナーだけじゃないですか、ぶっちゃけ。
ってか、さらにぶっちゃけると、そのヘッドライナーのバンドが単独ツアーでの集客に不安が残るから、
「注目の若手バンドも前座で観れてお値段は通常通り!」
ってお得感出したパッケージングで運営してるのが実情かと。
そこに駆り出される若手バンドは、
「ガンズやスキッド・ロウのファンたちにも観てもらうことができるから、良い宣伝効果が期待できるよ!」
なんて口車に乗せられてやるんだけれども、お客の誰も真面目には聴いてないわけ。
そんなんやるくらいなら、ホール規模(2000人クラス)でもいいから単独ツアーやったほうがまだマシなんですよ。
この扱いに関して彼らもいい加減うんざりしていて、当時のインタビューでも
「もう前座はまっぴらだ。自分たちの単独ツアーをやりたい」
なんてことを漏らしてます。
よっぽどガンズとのツアーでストレス溜めたんだろうな~。
「奴らとのツアーは、アクセルのワガママにかなり振り回される」と、あのメタリカでさえ漏らしていたくらいなので(笑)。
そして念願かなって、この『スーパーアンノウン』のプロモーションツアーでは単独ツアーが実現します。
そのスタートがなんと日本だったんですよ。
『スーパーアンノウン』がリリースされる1ヶ月前、つまり1994年2月からの初来日がそれにあたります。
実はこの初来日時のライブ、およびインタビューなどが『ミュートマ』(ミュージックトマト)で特集されたものをYoutubeで見つけました⇩
これはサウンドガーデンの資料としては、数あるお宝映像の中でもSクラスと呼んでもいいほど超貴重なものですから、
正座して観てくださいね。
こういうのを探してたんですよ、ようやく見つかりました。
これって、ご家庭のVHSビデオで録画してたものをアップしてくれてるんでしょ?(アップ主が日本人じゃない?)
しかも『ミュートマ』って番組はテレビ神奈川ですよ?
ローカル放送なんです。
こんな貴重なものがよくぞ2020年代まで生き残ってたもんだ。
こういう貴重な映像を共有できることこそ、Youtubeひいてはインターネットのそもそもの価値だと思うんですよね、本来は。
で、見どころ満載の動画で語るべきことは山ほどあるのですが、この動画から分かる重要なポイントを簡潔にまとめるとこんな感じでしょうか?⇩
①日本でサウンドガーデンが最初期に紹介された頃は、ヘヴィメタルバンドと受け取られた(マサさんが推してれば話す内容に関係なく誰だってメタルバンドだという先入観で聴くでしょう)
②オープニングアクトという扱いを辞めて単独ツアーをやりたがっていた
③日本でのライブは、動画を見るかぎり一定数のコアファンは盛り上がっている。また、ツアーの最初期のためクリスの声が最高のパフォーマンスを発揮している(ここまでのパフォーマンスはレア中のレア)。
④『スーパーアンノウン』のプロデューサー、マイケル・ベインホーンとの仕事に関しては、まったく満足していない(かなりムカついている、思い出したくないくらい)
⑤サウンドガーデンは全員が原曲を持ち寄るバンドではあるが、それを皆で練り上げていく制作方法をとっているので、すべての楽曲はバンドメンバー全員で作曲していると言っても良い。
サウンドガーデンって日本での人気が絶望的なほどないから、情報が少なすぎるんですよ。
この動画はほんと貴重です。
で、『スーパーアンノウン』はその後に大ブレイクしちゃったんで、このワールドツアーは伸びに伸びて2年くらい続くことになります。
地獄です(笑)。
クリス本人も
「こんなガラガラ声で金を取ることが申し訳ない」
というほど声がボロボロの状態でツアーを続けていたとのこと。
そう、尋常ではないほどのハイトーンボイスを駆使するサウンドガーデンのライブは、明らかにツアー向きではないんですよ。
それだけに、日本での公演は実はかなりラッキーだったんですね。
ただ、ブレイクする前に来てしまったので、誰もその有り難さが分かっていなかったという(笑)。
『スーパーアンノウン』の内容に関する質問では、クリスもベンも自信なさげにうつむき加減でボソボソ喋るから、
「え?なに?聴いちゃいけない質問だったの?もしかして新作は失敗作なの?」
って観てる人は思ったはずです(笑)。
「新作はより洗練され多様な音になってますね」
と言われた時のクリスの心底嬉しそうな顔ときたら!
思いっきり素の表情で「ありがとう」って言っちゃってますよ(笑)。
このテレビ慣れしていない感じが、
「それまでは、ほんと売れてなかったんだな~」
とかモロに感じてしまいます。
それと、マイケル・ベインホーンは当時売れっ子プロデューサーだったのですが、『マザーズ・ミルク』で起用したレッチリも、

『マザーズミルク』
『オズモシス』で起用したオジー・オズボーンも…
誰も良く言わない(笑)。
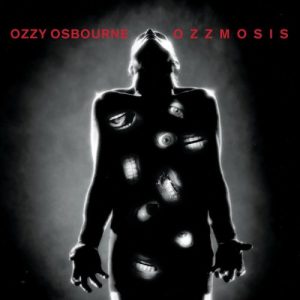
『オズモシス』
ジョン・フルシアンテは不本意なメタルのギタープレイを強要され、オジーは何度も何度も歌い直しをさせられ…。
スポーツの鬼監督のようなノリで、プロデューサーのくせに作曲段階から介入してくるっていう始末が悪い男なのですが、この強烈なキャラクターがバンドの反骨精神と仲間意識を育ててしまうのか?
結果だけを見ると、決まって傑作が生まれてしまうという謎の現象が起きます(笑)。
「え?この話の流れで何故そうなるの?」
と思われるでしょうけど、ホントにこの人が関わると、ことごとく素晴らしいことになるんですよ、実際。
いちリスナーとしては
「グッジョブ、マイコー!」
って称賛してあげたくなるのですが、一緒に制作したアーティストたちは堪ったものではないようです。
ただ、この時のことがトラウマになり、本作『ダウン・オン・ジ・アップサイド』はセルフ・プロデュースとなります。
来日インタビューで、アルバムの出来に関して不安な様子が見て取れたのは、まだリリース前で売れ行きも分からなければ、ライブでのお客の反応も分からない段階だからしかたのないことでしょう。
「もしかしたらファンたちにそっぽを向かれる作品が出来上がってしまったんじゃ…(マイコーにそそのかされたせいで)」
みたいな不安がありながらもツアーを続けていった先に、世界中での大ヒットと大歓迎が彼らを待ちうけているとは、この時点では1ミリも思っていなかっただろうな~(笑)。
マイコーはやっぱただモンじゃねぇな。
『ダウン・オン・ジ・アップサイド』で変わったこと
超分厚いサウンド作りで聴く者の聴覚を音塊でぶん殴ってきた前作『スーパーアンノウン』。
他のグランジ・オルタナバンドたちの追随を許さない圧倒的個性を確立しました。
しかし、意外にも彼らは本作において、その作風を踏襲しませんでした。
というよりも、エンジニアとしても能力の高かったマイコーと袂を分かったからには、あの音作りは再現できないのかも。
こうしてブログを書いてるので、この間までは『スーパーアンノウン』を聴きまくっていて、そこから改めて本作を聴いてても、1曲目『プリティ・ヌース』を聴いた瞬間
「音が薄っ!スカスカやがな!」
って驚きます。
リアルタイムの当時はそう感じてはいなかったはずなんですが、やっぱり前作と聴き比べるとその差は歴然。
そして何より“そこまで重くない”。
これが最大の特徴と言ってもいいでしょう。
まあそうは言っても、あくまでサウンドガーデンのそれ以前の作品と比べてであって、一般的なロックの範疇においてはしっかりヘヴィネスしてるし、音の厚みも’70年代以前の作品に比べれば十分あるのですが。
こうした変化はどうしてかというと、まず1つ目が先述したマイコー・プロデュースからの反動でしょう。
あまりにもガミガミとダメ出ししてくるので、そりゃあ真反対のことをやりたくもなるってものでしょう、人間なら(笑)。
あまりにも制作時間が長かった前作から比べると、今回はサクッと作り上げました。
密室的に作り込むことをやめて、よりオープンなライブ感を重視しており、ベンは本作を評して
「サウンドガーデンの実際のサウンドを最も正確に表した作品。はるかに生々しく、はるかに正直で、はるかに責任感がある」
と語ってます。
これはまさにその通りに感じましたね、当時は。
先の来日インタビューで
「レコーディングとライブの音は別物」
と言っていたのとは対照的です。
つまり前作とは真逆の制作プロセスを意図していたことを意味します。
そして2つ目がクリス・コーネルの嗜好の変化が挙げられます。
今作の制作にあたって、これまで通りヘヴィなリフをメインに据えた路線で制作したいキム・セイル(ギター)と、より歌にスポットが当たる作風にしたいクリスとの間で意見の対立が起きます。
これもマイコーがいなくなったことの反動といえばそうでしょうね。
ようはマイケル・ベインホーンはあまりにも強権発動だったので、共通の敵(=マイコー)という壁を前に一致団結できたんですよ、前作の制作時は。
彼がいなくなりセルフ・プロデュースとなったことで、メンバー同士が衝突する機会が増えるわけです。
バンドって難しいよな~。
サウンドガーデンっていうバンドは、もともと最初の頃は、キムがメインで作曲してて、徐々に作曲に慣れてきたクリスやヤマモトが作ったナンバーが増えてきてました。
で、ヤマモトから交代したベン(ベース)が加入してからは、マット(ドラム)も積極的に原曲を持ってくるようになり、相対的にキムの作曲する曲が減ってきてたんですよね。
さらに言えば、クリスとキムの共同作曲が減ってきて、クリスとベンの共同作曲が目立つようになってきます。
バンドの中でのキムの発言権が弱くなってきたのか、インタビューを受けるのも来日時のようにクリスとベンの二人で受けることがほとんどです。
昔はほとんどキムとクリスが喋ってたのにね。
そういう流れがあったこともあり、ここで自分が持ってきていたヘヴィなリフのアイデアまで
「もうこれからはそういうリフは必要ない」
と言われたも同然のキムからすると
「おいおい、もうこのバンドに俺なんて要らないってのか?」
っていう気分にもなるってものでしょう。
そんなキムの本作における作曲はたったの1曲。
クリス7曲、ベン6曲、マット2曲。
これって、淋しい事実のようで、頼もしい事実でもありますよね。
それだけバンドメンバー全員の作曲能力が全体的に上がってきたということなのですから。
ビートルズで言うとジョン、ポールに次ぐ3人目の天才としてジョージが覚醒してきた、みたいなものですから。
で、前作までのように共作はなく、各自のソングライティング技術が上がってきたこともあり、単独作曲のナンバーのみで構成されています。
しかし、だからといって本作の各曲がバラバラの作風かというとまったくそうではなく、全てサウンドガーデン色に染まっているので、彼らにとっては原曲はあくまで“たたき台”であることが伺えます。
まさに来日インタビューで語っていたとおりですね。
誤解しないでいただきたいのは、クリスはリーダー的なポジションではあっても、強権発動して
「この曲はこういうふうに演奏しろ!」
っていうタイプの人ではないってことですよ。
マイコーとは違うのだよ、マイコーとは。
キムも作曲では貢献できてないし、ヘヴィなギターリフを減らす(抑える)ようには言われてるけど、ガッチガチに命令されているわけじゃなく、ギタープレイに関してはかなり自由にやれているわけです、実は(本人談)。
こういう度量の広さがクリスという人の凄さであり、テンプル・オブ・ザ・ドッグやオーディオスレイブをまとめ上げるだけの“規格外の器の広さ“を持った人なんだと思いますよ。
こんな制作プロセスを辿っても収拾がつくというのは、なかなかの神業というか(笑)。
メインの作曲者の独裁状態になるバンドも多いなか、サウンドガーデンはメンバーが横並びで民主的です。
だからこそメンバー1人1人の個性が際立つんですよね。
バンドのあり方としての理想像ですよ(ZEPやオリジナルサバスと同じく)。
『ダウン・オン・ジ・アップサイド』楽曲解説
実は前作『スーパーアンノウン』では封印されていたサウンドガーデンの必殺の武器が、本作では復活していることに気がついた人もいたかと思います。
それは『スピードナンバー』の存在です。
彼らの初期作品が特に好きな私にとって、1作目の『サークル・オブ・パワー』『ナチ・ドライバー』、2作目の『ガン』『フル・オン・ケヴィンズ・マム』、3作目の『ジーザス・クライスト・ポーズ』『フェイス・ポリューション』といった、各アルバム2曲程度入っていたスピードナンバーは、もうアドレナリンが出まくるナンバーなんですよ。
サウンドガーデンの音楽的特徴って、ヘヴィでうねったギターリフ、クリスのハイトーンボーカル、変拍子の多用、トリッキーなドラムプレイなどが認知されていると思うのですが、サウンドガーデンの魅力の一つに実は『速さ』、つまりハードコアな側面があることはあまり話題に上らないというか。
『スーパーアンノウン』には「わりとアップテンポなナンバー」はありますが、「スピードナンバー」と呼べる曲は1曲もありません。
入っていたとしても、果たして前作の分厚いサウンドにスピードナンバーが合っていたのかどうか?
非の打ち所のないサウンド作りをマイコーと追求しすぎたあまり、実は「感情・衝動の爆発」というサウンドガーデンの持つハードコアな魅力が発揮されていなかったように感じます。
本作中ではスピードナンバーが3曲もあり、過去最多です(あくまで私基準です)。
このスピード感が復活したのは思わずガッツポーズでしたね。
クリスも本作を評して
「(前作で)音の精度で失ったものを、(本作で)感情の面で多くを得た」
と絶妙な表現をしています。
もちろん、この発言は単にスピードナンバーを収録したことだけを指すわけではありませんが、完成度(作り込み)よりもエモーション(感情)を優先した結果、感情の暴走したスピードナンバーも生まれたし、レイドバックしたような初めて見せる一面も出てきた、ということでしょう。
武装していない、『素』のサウンドガーデンが聴ける作品です。
また、“スピードナンバー”もそうなのですが、アングラさだったり、ルーズさ、パンキッシュさだったり…、ミュージシャンとしての進化の過程で削ぎ落としてきた要素を再び取り入れていると言うか。
なので、本作はインディ時代から前作までのアルバムごとに見せていたエッセンスを全て含んでいます。
「あ!この雰囲気ってあのアルバムのあれっぽい」
みたいな瞬間がけっこうありますので、やっぱり集大成としての意識も少なからずあったんじゃないかな。
解散前のラストアルバムとして相応しい作品だとつくづく思います。
でありながらも、これまでになかった新しい要素も加えてるのが凄い!
楽曲ごとのサウンドカラーは『スーパーアンノウン』も多彩でしたが、今作は『感情』が多彩、とでも表現すればいいですかね?
『スーパーアンノウン』までには一度も見せたことのない感情が見え隠れしていると言うか。
歌詞もサウンドも『陰』、『鬱』という負の感情が強く伝わってきていたこれまでと違い、本作には明らかに『陽』のエネルギーを感じますね。
サウンドガーデンのアルバムでまさかマンドリンの音色が聴こえてくるなんて、かつて想像できましたか!?(笑)
それでは楽曲ごとの解説行ってみましょう!
#1『プリティ・ヌース』
シングルナンバーで、本作では一番人気が高いかもしれない曲です。
まず、聴き始めの頃に気がつくのが
「このアルバム、マスタリングボリューム小せぇな!」
ってことです。
そのせいでえらく迫力にかけた印象を受けるんですね。
本作に対して「スカスカ」とか「ヘヴィさがない」という口コミが多いのは、このボリュームにも要因があると私は思ってます。
『スーパーアンノウン』などの過去作を聴いた後に本作を聴く時は、一旦ボリュームをグイッと上げて聴くことをおすすめします。
珍しくオーソドックスな4/4拍子で聴かせてくるのですが、この“間“や“タメ“が病みつきになります。
マットは1990年代ではかなり個性的なドラマーだと思いますね。
しっかし、改めて今回のクリスの歌は染みてくるな。
#2『ライノソー』
はい、やっぱり始まりました、得意の変拍子です(笑)。
彼らって実は変拍子を意識してやっているわけではないらしいです。
自然と浮かんできたメロディを組み立てていくと、変な拍子になっていることが多いみたいですね。
変則リズム⇨オーソドックスというリズムトリックの流れが、このサウンドガーデン特有の快感を生んでるんだと思います。
さらに、この曲ではサバスみたいな唐突のシフトチェンジまで入ってくるので楽しませてくれます。
#3『ゼロ・チャンス』
ここでゆったりとしたレイドバック・ナンバーの登場です。
前作の『フェル・オン・ブラック・デイズ』や『ブラックホール・サン』もゆったりしたナンバーではあったのですが、“レイドバック“と呼ぶには暗すぎる感情が匂い立っていました。
それに比べ、この曲の場合はより温かみがあるというか。
これまでに見たことのないサウンドガーデンですね。
#4『ダスティ』
もともとこの『ダスティ』の歌詞の中にあった
「I’m down on the upside」
が気に入ってアルバムのタイトルにしたみたいですね。
そこからも分かるように本作の『陽』の部分を請け負う曲ですね。
この曲とか聴くと、本作の“軽さ”がすごくよく分かります。
ギターの音とか、マッドハニーっぽいというか、インディの頃のEP『スクリーミングライフ』や『FOPP』が持つ雰囲気に近いと言うか。
#5『タイ・コッブ』
正確な発音はおそらく「タイ・カッブ」じゃないかな?
変な曲名に感じるかもしれませんが、古の偉大なる野球選手タイ・カッブのことです。
来ましたね、この迸(ほとばし)るほどのスピード感!
これは名曲であり、私がサウンドガーデンで一番好きな曲です。
こんな軌跡の名曲を彼らの他に誰が生み出せるというのでしょうか?
このアルバムを聴いた当時、それまで私の中で頂点に位置づけていた『バッドモーターフィンガー』の序盤5曲の神曲たちを超えてきましたね。
怒涛のスピード感でありながら変拍子をこれでもかとぶっこんでますし、全体のユニゾンが激しくうねります。
クリスのシャウトも最高ですが、キムのZEPばりのギターリフも最高。
っていうかマンドリンってこんな激しい曲の中でもこんなにクールに光るものなの!?
でも何より最高なのはやはりマットのドラムでしょう。
当時、スタジオに篭ってドラムの腕を磨きまくっていた若き日の私は、このマットのプレイにぶっ飛びましたよ。
発想があり得ない。
こんな発想ができっこない。
え?ベースのベンをスルーするなって?
何をおっしゃいますか。
この偉大な曲の作曲者ですよ。
ちなみに本国アメリカではチャート2位と、前作に続く1位獲得はならずだった本アルバムなのですが、オーストラリアでは1位だったため、この『タイ・カッブ』がオーストラリアでのみシングルリリースされました。
日本にも見習ってもらいたい…(日本では31位)
#6『ブロウ・アップ・ジ・アウトサイド・ワールド』
またしてもシングルナンバーです。
この囁くようなクリスも新機軸ですね~。
この後、ソロ、オーディオスレイブ、再結成という流れの中で見ても、クリス・コーネルのボーカルが全盛期だったのはこのアルバムであることは間違いないでしょう。
派手さもインパクトもないですよ。
けれども、この味は一体何なんでしょうね?
#7『バーデン・イン・マイ・ハンド 』
3曲連続でシングルカットナンバーです。
この曲は当時、深夜のカウントダウンTVか何かで見たんですよね。
この『サウンドガーデン人気底辺国家』とも言えるジャポンで、まさかサウンドガーデンの新曲のMVが見れるなんてほぼ奇跡です。
それほど、4枚カットされたシングルの中でも一番売れた、このアルバムのリードトラックとも呼べる曲ですね。
MVでは砂漠を歩いているのですが、この『行くも地獄、引くも地獄』という心境が当時のクリス・コーネルの心境だったようです。
相変わらず歌詞の内容は暗いのですが、音楽はサウンドガーデンとしては型破りなほどに明るく、ちょっとコミカルにさえ思えます。
これね、当時は一発で気に入ったんですけど
「これきっとすぐに飽きるやつだな…」
とか直感的に思ったものですが、あれから30年が経っても飽きていないという事実に今回驚きました。
ものすごく普遍性が高い名曲です。
『ブラックホール・サン』に匹敵する名曲だと私は思ってるんですが、世間の認識はそうはなっていないので再評価を期待したいですね。
興味深いことにどちらも『太陽』がキーワードになってます。
#8『ネヴァー・ネイムド 』
#4『ダスティ』以上の、思いっきりパンクナンバーが来ました。
これまた前曲に引き続きどこかコミカルに聴こえるんですよね。
いや、この曲の場合はモロというか(笑)。
すごいですよ、このアルバム。
なんとあのサウンドガーデンの音楽を聞いていて『楽しい気分』になれるのですから(笑)。
歌詞はほとんど読まない派の私なので、歌詞でなんと歌っているのかは知りませんが、音楽を聞く限り、ここには確かに『楽』の感情がありますよ。
それにしてもドラムで『楽』を表現しているマットのセンスに脱帽…。
#9『アップルバイト』
レビューでもかなり不人気が伺えたインストナンバーです。
いや、これは必要ですよ。
『楽』の雰囲気が2曲連続続いた後に、一旦箸休めで次のハードナンバーに繋げるっていうね。
CDアルバムで聴く時代だったからこその工夫でしょうが、現代であればこういうこともあんまりやられなくなりましたよね。
インストナンバーとは言いましたが、一応、歌詞があって、何やら呪文のような呪詛のような不穏な声が聴こえますね。
私だったらこの曲のタイトルは「サイケデリックNo.1」にするでしょう(笑)。
#10『ネヴァー・ザ・マシーン・フォーエヴァー』
これがキムセイル唯一の作曲ナンバーです。
この強靭なギターリフかっこいいな~。
9/8拍子のリズムがもたらす奇妙で病みつきになるグルーブ感がたまりません。
もう1,2曲はキム作曲のナンバーが欲しかったと心底思います。
#11『タイター&タイター』
個人的には嫌いじゃないのですが、若干キャラが弱いというか。
ハードでもなく、バラードでもなく、コミカルでもなく、スピードナンバーでも、超ヘヴィナンバーでもない。
だから地味に感じるのですが、クリスのボーカルだけを見ると感情移入度MAXっていう。
完全に歌を聴かせにきてるナンバーです。
#12『ノー・アテンション』
久々にきましたスピードナンバーです。
怒涛のように攻めてきますよ。
これこれ、これがあるからこのアルバムは楽しめる。
こういう攻撃力が『スーパーアンノウン』には足りてなかったんですよね~。
#13『スウィッチ・オープンズ 』
#9あたりから1曲ごとに緩急をつけて来てますね。
同じ雰囲気の曲を2曲続かせずに、リスナーの飽きが来ないように工夫されてます。
ここで初めて『スーパーアンノウン』のようなサイケでオリエンタルな雰囲気が出てきました。
これは前作でいう『Half』みたいな役割で、前作に入ってても違和感ないナンバーですね。
#14『オーヴァーフローター 』
サイケで浮遊感のあるナンバーです。
この曲好きなんだよな~。
このサビでのギターリフが染み渡ります。
でも、おそらくこのアルバムが好きになれない人は前曲、そしてこの曲あたりがその要因なんじゃないかな?
だって従来のサウンドガーデンファンの求める(期待する)音楽ではないので。
気持ちは分かります。
しかも、トータルがこれだけ長いアルバムの後半で出てくるナンバーとしては厳しい。
けれども、聴く順番なんてどうでもいいから、純粋にこの曲だけに耳を傾けてみてください。
非常に味わい深いです。
おすすめは寝入りっぱなに流すこと。
#15『アン・アンカインド』
ここにきて最後のスピードナンバーを持ってきてくれました。
本作は意地でも最後まで聴き通させる気です(笑)。
『バッドモーターフィンガー』の頃とは大違いですね。
この職人芸のようにあざやかな変拍子ときたらどうでしょう?
たったの2分ちょいで潔すぎるくらいスパッと終わります。
#16『ブート・キャンプ』
最後はレイドバックでゆったりとフィナーレを迎えます。
3分足らずのエンディングですが、当時サウンドガーデンが解散した時にはまるでカーテンコール(幕引き)の曲に聴こえたものです。
蜃気楼みたいに消えていくイメージ。
サウンドガーデンらしい幕引きだと感じました。
はい、今回は『ダウン・オン・ジ・アップサイド』をたっぷりと語ってきました。
これは名盤だし、『スーパーアンノウン』と肩を並べても良い作品だと私は思っています。
この記事が本作の再評価の一助となれば幸いです。
それではまた!