音楽解説で目指すもの~Simackyのつぶやき~13
こんばんわSimackyです。
超お久しぶりのつぶやきコーナーです。
前回は1月…ということは半年ぶりになるわけですね。
昨日仕上げた森高の記事で、このサイトでの累計がついに
300記事
に到達したんでね。
いやー、嬉しくて気が緩んだので、久々に肩の力抜いて語りたくなりました。
このつぶやきコーナーを始めた当初は、予想では3記事に1記事はつぶやきになると思っていたのですが(笑)。
ただ思いついたことをダラダラと語っていくので、書くのは楽なはずなのに意外にも書かない。
なんでか?
それは私の音楽解説記事を先入観抜きに読んでもらいたい、という思いがどうもあるようですね、無意識だったけど。
主義主張の強い、しかも独断と偏見で語りがちな人間なので、あんまりこういうフリートーク的なコーナーにはまってしまうと、ドン引きされてしまう気がしてね。
私の主義主張とか価値観とか、まあ、それがあるから音楽レビューも面白みが出るものだとは思うのですが、それを読む人に押し付けたくない。
音楽解説記事の主役は取り扱うアーティストであって、私が主役ではない。
そのアーティストの作品をどう感じるかは皆さんの自由。
ただ、こういう感じ方をしてこういう感想を持った、という一例を見せているに過ぎませんから。
私は、色んなデータを拾い集めて
「こういうデータが意味するところはつまりこういうことだ。」
というストーリーを作ります。
そのほうが面白いと思うからです。
けれども、それはあくまで私の仮定から生み出したフィクションであって、事実ではありません。
これってね、多分やってることは歴史小説に近いんじゃないかな?
例えば、司馬遼太郎の『燃えよ剣』っていう新選組ものとしては一番好きな愛読書があります。
あれはあくまで『歴史小説』であって『歴史書』ではないんですよ。
『三国志正史』と『三国志演義』の違いとでも言いましょうか。
歴史小説家はさまざまな記録、データから想像を膨らませ、キャライメージを作り、そのキャラたちの個性に合わせてストーリーを紡ぎます。
新選組として記録に残されている事実があったり、沖田総司や土方歳三の関係者の親族の話が残っていたり。
そういうものから勝手にキャラを作っていくわけです。
で、
「こいつならきっとこういう時、こう考えてこうやって行動するはずだ」
みたいな感じで話を膨らませていく。
うん、私がやっているのはまさにこれです。
ただ、歴史小説は取り扱う人物が『過去に生きていた人』であるのに対し、私が取り扱っている人物は『現代も活動中のミュージシャン』なんですね。
これまで語ってきたアーティストである、X、ルナシー、イエモン、サザン、ワンオク、オジー、REM、メタリカ、レッチリ、メガデス、ドリームシアター、アリス・イン・チェインズ、サウンドガーデンはほとんど生きて現在も活動中です(残念ながら無くなっちゃった人もいますが)。
つまり、歴史小説家と違い、私以上にその人物の人となりを詳しく知っている人は山のようにいるわけです。
そんな状況でこうして勝手にキャライメージを作って語っていくことが、果たして正しいことなのかどうか?
疑問に思うことはありますね。
まあ、これに関しては何が正解かなんてアーティスト本人にしたって分からないことではあるのですが、1つだけ気をつけていることがあります。
それはそのアーティストが好きなファン、そういう人たちがテンション上がるような記事を書きたい、と。
私が大好きなバンドのブラック・サバス(オリジナルメンバー期)を例に出しましょう。
私はサバスが大好きなんで、サバスの作品、そしてサバスのオリジナルメンバーが褒め称えられていると、我がことのように嬉しい。
まだ、私がこのブログを始める以前、こんな事がありました。
CDで熱心に音楽を聞かなくなり仕事に没頭してきた10年が終わり、ふと、音楽を聞きたくなった頃、ストリーミングという音楽の聴き方に出会います。
ストリーミングはほぼ全ての音楽を聴くことができる贅沢さがある反面、かつてCDの頃にはあった「ライナーノーツ(解説書)」が付いていない。
「久々にサバスを聴きまくっている傍らに、なにかこのアルバムに関しての情報がないと、ただ聴いてても寂しいな」
そう思うようになると、今度は自然とスマホでサバスに関しての記事を探し始めるわけです。
その時に出会ったサバス大好きっ子たちの記事の面白さときたらありませんでした。
「それそれ!俺もずっとそう思ってたのよ!よくぞ言ってくれた!」
もうアドレナリン出まくり(笑)。
テンション爆上がりでしたよ。
人って自分が感じていたことを言語化してもらうと、こんなに快感を感じるものなんだと知りました。
だったら
「もし俺が好きなアーティストのことこんな風に書いてもらったら鼻血出るくらい嬉しいんだけど」
っていう記事を自分で書こうと思いました。
これがいつも変わらぬ私の基本姿勢です。
そしてその時に知ったもう1つ大事なことがあります。
それはギャグ・ジョーク・笑いのツボ…そういったユーモアというものは、十人十色だということ。
例えばお笑い芸人であれば、10人中10人から笑いを取ることを目指さなければいけません。
それができるような人が人気が出て生き残っていく。
10人中1人からしか笑いを取れない人は芸能界で生き残っていけないんです。
つまり多くの人に伝わるユーモアのセンスを磨かなきゃならないし、そういう笑いを追求しなきゃならない。
それがお笑い芸人としての正解なんです。
けれども、ここはブログです。
私達はプロの世界での生き残りをかけてブログを書いているわけじゃありません。
ここでは正解が違うんです。
ユーモアは本来、十人十色。
10人いれば10パターンの正解があります。
その人なりの感性で感じたものを、その人なりの言葉で伝えれば、それはユニークなんです。
それだけで価値がある。
それは10人が読んで10人が共感することではないかもしれません。
けれども、10人読めば、その中で感性がぴったり合う人は1人や2人は出てくる。
そういう人からは
「よくぞ言ってくれた!なんかもうありがとう!」
っていう言葉が聴ける。
これがブログの醍醐味です。
なので、私は10人全員が喜んでくれる記事なんて目指してません。
ただ、「私が読者としてとして読んだら鼻血が出るくらい嬉しいかどうか?」それだけを物差しにして、明日も自分の言葉で、ありったけのユーモアを込めて記事を書くだけです。
さて、サウンドガーデン、クリス・コーネルを書いている途中で森高に走っちゃったけど、今後はどうしようかな?
森高に関しては書きたいこと全部書いちゃったんで満足したし、今更サウンドガーデンのテンションに気持ちが切り替わらない(笑)。
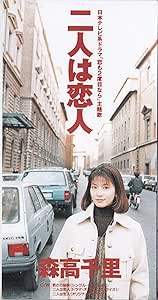

shimacyさんこんにちは
大好きだったロックスターが毎年のように旅立ってしまいますね、寂しいものです。
もう二度と見れない、といえばパンテラも一度でいいから生で見てみたかったバンドでした。
もし機会がありましたらパンテラのレビューもお願いします。ドラマーならではの目線もすごく興味がありますので是非レビュー拝見したいです!
KAさん コメントありがとうございます!
ついにパンテラのリクエスト着ましたね~(笑)。
実はアリス・イン・チェインズ、サウンドガーデン、オーディオスレイブと来たので、次の候補はレイジかパンテラか?って考えてたんですよ。
パンテラはZEP、レッチリ、サウンドガーデンと同じく大学時代に一番コピーしたんじゃないかな?ヴィニー・ポールの影響で3年くらいスティックを逆に握って使ってましたし(笑)。
最近、森高、アンジェラと女性アーティストに浮気してしまったので、そろそろパンテラ行きたいのですけど、しばしお待ちを!
simackyさんは、ピンク・フロイドなんて聴かないですか?
森高千里関連のブログしか読んでないですが、フロイドの印象とか聞けたら面白そうかななんて思いました(笑)
しゃらく。さん
続けてのコメントありがとうございます!
ピンク・フロイドですか!?
いや~、実は…昔は『狂気』にはまって聞いていた時期があります(笑)。
やっぱり音楽的評価が高い人達なんで、その頃に一応、オリジナルアルバム15枚は全て聴いてみたんですが、まだまだこうしてブログに熱く語れるほどの温度感にはなってませんね。
そういうアーティストって自分の中では結構いて、ストーンズ、ボウイ、プリンスなんかもそうで、もうちょっとのめり込んだら書くのにな、みたいな(笑)。
まあ、感性は年齢とともに変化していきますんで、そのうちフロイドにビビッと来た時には書くと思いますよ。
その時は是非読んでみてくださいね!