「at the Black Hole」吉井和哉ソロデビューアルバム
本記事はプロモーションを含みます。

どうもsimackyです。
本日は吉井和哉ソロデビューアルバムの
「at the Black Hole」
を語っていきたいと思います。
ちなみに最初の2枚のアルバムは「yoshii lovinson」名義、「39108(さんきゅうひゃくはち)」からが「吉井和哉」名義となるのですが、このブログでは『吉井和哉ソロ』ということで一括りにして扱います。

なので「39108」は3作目として扱います。
初のソロ作品が生まれるまでの苦労
さて、2001年に初の東京ドーム公演を終えたイエローモンキーは活動休止に入りました。
当時リアルタイムの我々からすると、一時的な「活動休止」であって、解散とは受け取っていませんでしたが、ロビンこと吉井和哉の心の内、そしてバンド・イエモンの内情としてはほぼ終りを迎えていました。
その証拠にこの休止期間中は本当に一切の活動は行われず、そのまま2004年に解散してしまうからです。
ロビンは東京ドームが終わった1月には、もうソロ楽曲の制作に取り掛かっています。
別に「at the black hole」っていうアルバムを作るつもりでの制作ではなく、最初はただ単に作っていただけらしいのですが、アルバムのリリースは2004年7月なので、制作期間がなんと
3年半
にもおよびます。
ちなみにイエモンでそんな制作期間をかけたことは一度もありません。
まあ、これは単にアルバムリリースの契約がない状態から作っていたから、そうなったのもありますが、音楽制作環境が変化したことも理由として挙げられます。
具体的にこの頃のロビンは一体どんなことしてたの?ってことなんですが、最初の頃は1人MTR(ハードディスクレコーダー)の前に座って、シコシコと作曲活動をしてました。
しっかり父親として子育てしながら。
子連れロッカー状態ですね(笑)。
この頃は、インディ版「バンチド・バース」、最高傑作「シックス」以来となる、3度目の『創作欲求の爆発』が起きていたとのこと。
「うおおお、創作のエクスタシーがやってきたぞぉ!」
みたいな。
実はMTRなんかを使うのがこの時初めてだったらしく、自分でどんどん録ってすぐに曲が形になることに感激し、取り憑かれたように作曲に明け暮れたとのこと。
その時期にすでに本作収録の「TARI」「20GO」は出来てて、デビッド・ボウイの中期みたいな曲や、オジー・オズボーンみたいなメタルの曲まで、ノンジャンルで色んな音楽を作っていたらしいんです。
自身の作品の出来には大満足で
「もうこれレコーディングとかしなくてこのまま出しちゃえばいいじゃん!」
ってくらい気に入っていたとのこと。
と、ここまで聞くと、
「家庭も円満、音楽制作はやる気満々で充実してるじゃん。」
って思えるのですが、だんだんと不安な気持ちに襲われます。
「いや、あれだけの大企業(イエモンのこと)やめたんだから、それを超えるくらいのをだ出してくんないと困るんですけど」
みたいなプレッシャーがだんだんと出てくる。
そうなると
「俺がイエローモンキーをやめたのはこういう理由なんだ!っていうものを作りたい」
っていう意地が出てき始める、と。
で、ここからのレコーディングが、完全に泥沼化しちゃって葛藤の日々に陥っちゃうんですよ。
どうしてそうなったのか?
ロビンが自伝で語っていることは、話が飛んだりして、読んでていてちょっと分かりづらいので、簡潔にまとめますね。
イエモン以上のものを期待する人たちを驚かせるようなものを作りたい。
けれども、自分はイエモンという恵まれたプロの環境の中で、腕利きのメンバー達と作るやり方しか知らない。
それに対し、今自分がやっている制作方法は極端に密室的で、エンジニアリング的な知識が必要だというのに、自分はそれまで完全に人任せにしていて、ノウハウが全く無いことを思い知らされる。
じゃあ、バンドっぽい音を作れるかというと、それも技量が足りない。
宅録したものをレコーディングスタジオで自分で録り直すと、まったく納得できる音に仕上がらない。
しかたなくドラムだけは人に頼むけど、バンドで1回挫折しているから、またバンドという編成を組んでこれを仕上げる気にもならない。
「じゃあやっぱり1人で作んなきゃ」
と、これを仕上げられるエンジニアを探していろいろな人に当たるけど、腕利きの人だと今度は自分の音楽の世界観を壊しにかかってくる。
さて、どうしたものか?
というわけで、色んなエンジニアと試行錯誤を繰り返し、アメリカと日本を行ったりきたりしているうちに、疲労困憊になってきて、演奏やボーカル録りのパフォーマンスも落ちてくる。
パフォーマンスが落ちると録り直しも多くなるという悪循環。
そして最後には過労で倒れる、と。
ソロ1作目って、イエモンの激務が終わり、隠遁生活ののんびりした空気感の中で作られた印象があったのですが、実情はまったく違ったようです。
全盛期の頃のようなツアーやテレビ出演こそないものの、結構たいへんな日々だったみたいですね。
イエモン活動休止の最中に生まれていた最初にして最大の異色作
本作のレビューや批評を読んでいると、
「暗い、ダーク、内省的」
とかいう表現が多いです。
私も実際、最初の頃はそう思ってました。
その原因はイエモンの『華やかさ』がないからだと思いました。
「ダーク」「内省的」はイエモン時代から濃厚にありました(特に初期)。
ロビンは結構もとから根暗です(笑)。
ただ、イエモンには分かり易いほどの『華』があったんですよ。
まずロビンの歌い方。
これが明らかに意図的にイエモン時代と変えている。
ロビンの「歌謡ロック的な歌唱」の封印が大々的に解かれるのは、6作目「アップルズ」からだと個人的には思ってます。

『The Apples』
「アップルズ」を聴いた時に
「ああ、これまではイエモン時代のように歌えなくなったんじゃなくて、わざとそうやっていたのね」
って全てが分かりました。
いや、もっと早く気付けよ(笑)。
そのため、本作には、いえ、ここから2作目『ホワイトルーム』3作目『39108』の3作には、あの圧倒的なまでの存在感、ロックスターとしての存在感が無くなってるんですよね。
もちろん、『脱ロックスター』のため、『イエモンとソロの線引のため』に、あえてそうしているわけです。
さらにヒーセの躍動感のあるノリノリのベースもありません。
ギターに関しては強烈なインパクトのあるエマのリフはないどころか、あえてエマは決して弾かないであろう『オルタナ的なコード』なんですよ。
聴いていると、ニルヴァーナ、ソニック・ユース、ダイナソーJr.、ストーン・テンプル・パイロッツなんかを思い浮かべてしまうんですよね。
「TARI」のイントロのあのヒステリックな響きからしてモロにそうですよね。
けれども、それらの『物足りなさ』って、かつてのイエモンのイメージとの落差からくるものであって、
「じゃあ、イエモンを聞いたことがない人の耳で聞いた時に、果たしてどうなのかな?」
とは思います。
現にずっと私もそのギャップを受け入れきれずに、ソロ作品は遠ざけていた節がありますので、ここ最近ソロ作品を徹底的に聴き込んで、イエモンから『1回離れた耳』で聴くようになると、これが意外にそうでもない。
これはこれで味がある。
っていうか、イエモンは受け付けないけど、こっちなら受け付ける人もいるでしょうね。
我々イエモン好きが好む濃厚なエッセンスは、イエモンが苦手な人からすると
「いや、それがちょっと無理なんだって」
って感じるわけであって、その濃厚エッセンスが薄くなった本作なんかは
「あ!これならいい!」
ってなる可能性があるんですよね。
これまで見せてこなかった吉井和哉の新たな魅力がここにはあります。
ただ、いかんせんイエモンで10年以上築いてきた1つのスタイルを捨てて、新たなスタイルを目指しているわけなので、そう安安と1枚目のアルバムなんかで新スタイルを確立できるまでには至っていない、といったところでしょうか?
それにボーカル録りに集中できるほどの制作環境でもなくて、わけ解んないことを全部1人でやっているわけだから、しょうがないでしょう。
もうバンドのボーカリストではなく、ギタリストでもあり、ベーシストでもあり、プロデューサーでもあり、ミキシング・エンジニアでもあり、と、全てに携わんなきゃならない。
そして今回は『音のクオリティ』というエンジニアリングの部分で壁にぶつかりまくっているので、歌い込んでボーカルのクオリティを上げていくというところまでたどり着けなかったということでしょう。
そう、特にこのソロ1作目におけるボーカルの位置づけというのは、ロビンの中では「作品を構成する数ある要素の1つ」でしかなかったのではないでしょうか?
他のパートやらもろもろを他の人に任せて、ボーカルに専念できているわけではないので。
ただ2作目収録の「call me」では早くも
「おお!ニュー吉井和哉もすげぇぞ!」
って唸らせてくれるので、やっぱり只者じゃないとは思いますね。
2作目から他の楽器を人に任せてるから、その分、ボーカルへの比重が大きくなったんでしょうね。
まあ、そういうわけなので、吉井ソロの7枚のアルバムを聴き通してみても、やっぱり初期3作、特に本作はかなり異色です。
ロビンは自伝で
「良いと思うのは最初の3曲だけ。もう一巻の終わりと思ってた。できれば出したくなかった」
と評している一方で
「後から振り返ってみると、精神的にはこのアルバムを今後超えることは出来ない」
とも言い、本作を「傑作」とも呼んでいます。
しかし、当時は雑誌のレビューでも散々叩かれたことでかなり落ち込み、
「まだイエモンという逃げ道に未練たらしく期待を残しているから、こんなウジウジした作品が出来上がるんだ」
と、イエモンの正式解散を決断するに至ります。
まあ、確かにイエモンというものを引きずっている期間中にリリースされた作品のため、また「ブラックホール」というタイトルが付いていることもあり、暗く内省的なイメージが付いて回る作品ではあるのですが、実は本当に人生のどん底に陥るのは2作目の制作中なんですよね。
本作制作の期間中である2001~2004年という期間は、父親として至極真っ当な日々を送っており、音楽内容に満足はいっていないとは言え、女遊びも酒もやめて家庭は円満だったみたいです。
けれども、解散発表と同時に山梨に家建てて引っ越しちゃったもんだから、それが原因で夫婦関係が悪化し、解散から4ヶ月後には愛人作って家を出て、飲んだくれのクソ野郎になっちゃいます(笑)。
次作「WHITE ROOM」こそが本当にどん底の時期の作品なんですよ。
けれども作風は本作よりもぐっと垢抜けた印象があるというか、『開けた』イメージが残るというか(あくまで本作に比べたらですよ?本当に開けた印象を受けるのは4作目くらいかな?)。
幸せだと作風は明るくなり、不幸せだと作風が暗くなる、というのは所詮、聞き手の勝手な先入観でしかないんだな、と気が付かせてくれます。
すべて1人でやるからこその究極の調和
本作を聴きこんでいて、
「こ、この感覚は…あぁ…あれ!あれだ!」
頭の中をよぎった過去の記憶があります。
レニー・クラヴィッツです。
昔、大学生の頃
「レニー・クラヴィッツがいい」
という噂を聞いて、レニクラのこれを聴いてみました⇩

レニー・クラヴィッツの1989年デビューアルバム
「レット・ラブ・ルール」
ですね。
とんでもない作品です。
聴いてすぐには絶対に名盤だなんて思わない名盤なんです。
大学生当時の最初の感想は
「うわ、音ちゃっちぃ。何この古臭い音?70年代?え?いつの人?90年代?嘘でしょ!インディ丸出しじゃん。ってか演奏もヘッタクソだな~。デモテープじゃないんだから。特にドラム!素人か!?ちょっと俺が叩いてやるからドラム替われよ!」
とまあ、ボロくそだだったわけです。
なんでこんなのが話題になってるのか意味わかんない。
しかも、バリバリにロックなヴィジュアルで、スラッシュ(ガンズ)のビバリーヒルズ高校同級生でしょ?
なのに、全然ハードなロックじゃない。
ほぼバラードといえるタルいテンポ。
ストーンズを初めて聴いた時もかなり面食らったのですが、それよりも
「そりゃロックって呼べるのか?」
って思いました。
「なんか…、ロックってもっと激しいもんだろ?」
みたいな。
しかし、不思議なことに、私はこのアルバムをMDウォークマン(懐かし!)に入れて、どこに行っても聴き続けることになります。
なぜか?
それは
耳に心地よかった
からです。
この音は『ちゃちぃ』ではなく、『温かみ』があり、『下手な演奏』には『味がある』ということが、聴くにつれ分かってきます。
そして何より、各楽器パートが『調和している』んですよ。
超絶にキレッキレのプレーなんてどのパートにもありません。
おそらくドラマーの私が『演奏が拙い』と感じたように、ギタリストやベーシストをかじった人であれば、『拙い』と感じたことでしょう。
けれども、それらがバチバチと喧嘩せず、調和しているんです。
「『全てを1人で録る』ということはこういうことか」
と思いました。
本作『AT THE BLACK HOLE』もこれに通じるものがあります。
ドラム以外は全てロビンが1人で録っています。
エマのキレッキレでインパクト抜群のリフはありませんし、ヒーセのぐいぐい引っ張っていくメロディアスなベースも、アニーのオカズ多めのドラムもないです。
けど、それら音のすべてが控えめながらも調和しているので、聴いていて心地いい。
その音は理由があってその音になっているし、そのプレイも理由があってそのプレイになっていることが分かります。
唯一ドラムだけがセッション・ミュージシャンが叩いていますが、打ち込みの楽曲もあります。
打ち込みのリズムなんて、安っぽいリズムマシンみたいな音しているのですが、これが不思議と気にならない。
というより、生ドラムであれば曲の雰囲気を壊してしまったでしょう。
#4『SADE JOPLIN』を聴いてみてください。
『音の調和』という意味で、この曲なんかがまさにそういうナンバーです。
バンドではなくなったことで、半減する魅力もあれば、バンドではないからこそ表現できることもあるということですね。
各楽器のエゴなんて全く無いから、全て『曲を良くするためのプレイと音』になっているということです。
すべての楽器が『楽曲の世界観を完全に理解した人=ロビン』によって録られているので、ブレがないんですね。
例えばイエモンの後期の方であれば、
「エマちゃん、本当はここのプレイはもっとこうしてほしかったんだけどな~」
っていうこともあったと思うんです。
けれども、やっぱりバンドなんで、エマらしく弾いてもらわないと「そもそもバンドってなんだ?」って話にもなるわけで。
つまりロビンとしては、『エマの個性』を優先することで『楽曲の世界観』を妥協している部分もある。
これはギターだけじゃなく、すべての楽器がそうです。
本作の場合は『バンドメンバーの個性』がなくなった分、『楽曲の世界観』に向かってブレずにプレイされている、といったところでしょうか?
個人的にはバンドサウンドが大好きな人間なので、こうした作風は物足りなさを感じる私ではあるのですが、ただいかんせん楽曲の世界観の素晴らしさには心を打たれます。
確かに、本人が言っているように、この世界観の表現レベルはこの先も超えることが出来ないのかもしれませんね。
やっぱりロビンのソロ・アルバム7作品を全て聴き込んだ時に、初めてこの作品の放つ”重さ”が分かってきますね。
『人に伝える』『人に伝わる』楽曲を目指すとことと、『自分が納得する』楽曲を作ることの違いというか。
『人に伝える/伝わる』作品を作ろうとした時に、それまで自分がこだわってきたものが、
「こんなものリスナーにとってはどうでもいいことじゃん。自己満のこだわりじゃん」
って気がつくこと多いと思うんですよね。
これってどのミュージシャンでも陥ってしまいがちな壁だと思うのですが。
けど、「本当に『伝える/伝わる』ということが正解なのか?」と、本作を聴いていると考えさせられます。
リスナーの耳に合わせるってことは、我々リスナーの想像の範囲内に作品の可能性を収めてしまう行為というか。
我々の想像を超えてくるほど深みのある作品にはなってこないのかな、と。
リスナーが想像もしてないほど、どうでもいいようなこだわりが込められているからこそ、リスナーが聴き込めば聴き込むほどどんどんその面白さに引き込まれていくというか。
そういう作品こそ、我々リスナーに音楽の奥深さを教えてくれるのではないでしょうか?
リスナーなんてたまに置き去りにするくらいが本来のミュージシャンのあり方なのかもしれません。
そこで我々リスナーは新たな感性を発掘され、いずれはそこについていくようになるんですから。
本作は、込められているアイデアだったり想いだったりが深い分、聴き込めば非常に情報量の多い作品であることが分かると思います。
ロビンのソロは4作目『ハミングバード』あたりから、かなり開き直ってポップでオープンな作風になっていきます。
分かりやすくいうとイエモンの『スマイル』『フォーシーズンズ』あたりの作風に近づいていきます(笑)。
ノリが良く、ライブ映えし、とっつきやすく、シンプルなのですが、意外というかやっぱり飽きるのが早い(笑)。
しかし、『長く付き合える作品』という意味では初期の3枚、特にこのソロデビュー作はとびきりのスルメだと思います。
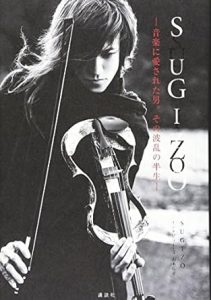

今度は吉井さんのソロの記事ですか。
また、しばらく楽しみができました。
吉井さんはこのアルバムの出来にショックを受けたかもしれませんが、リアルタイムで追っていたファンとしてはそれ以上にショックでした。
陰々滅々とした作りで。キャッチーな歌もないし。なんというか私小説的な暗さがあったんですよね。
これ聴いたこと忘れようと思ってしまったほど。
だから、ロビンソン時代はコンサート行く気がしなかったです。
そもそも、なに?ロビンソンって。恥ずかしいよ、と。今で言う共感性羞恥を刺激されまくりでした。
ともあれ記事待ってます。
コメントありがとうございます!
『共感性羞恥』確かに!。ツボってしまいました(笑)。
この1作目はまさに『リアルタイムで正当に評価することが困難な作品』の代表と言っても良いかもしれませんね。
これを「分かれ!」って言われても、みたいな。
私も最初20回くらい聴いても、メロディもビートも全てが何も入ってきませんでした。
しかも本人評価の高い「20GO」「TALI」の良さがさっぱり分からなくて、今回の聞き込みで「20GO」がツボり始めた時にパ~っとアルバム全体の良さが見えてきた感じですかね~。
なかなか味わい深いスルメ版です。